概要
一般の耳鼻いんこう科疾患(みみ・はな・のど)に加え、顔面外傷や腫瘍性疾患を含む頭頸部外科(首から上の外科)まで幅広く診療をしています。めまいの専門医によるめまい外来は毎週水曜日の午前中に行っています。
診療内容
耳(滲出性中耳炎・真珠腫性中耳炎・慢性中耳炎・顔面神経麻痺・めまい)
滲出性中耳炎は小児でよく起こり、原因はアデノイド肥大と言われています。治療はアデノイド切除と鼓膜チューブ挿入術を行います。慢性中耳炎や真珠腫性中耳炎では鼓室形成術を行います。また、顔面神経麻痺の重症例では顔面神経減圧手術を行うこともあります。
鼻(副鼻腔炎・アレルギー性鼻炎)
副鼻腔炎の手術はほとんどが内視鏡下で行われます。当院ではナビゲーションを使用し手術による副損傷を防いでいます。ナビゲーションとは、手術前に撮影した画像を3次元に構築し、手術中に3次元画像と術野の位置関係をリアルタイムにコンピューター上で処理することで、手術を補助する目的で用います。その結果、誤って頭蓋内や眼窩内へ侵入することが防げます。
のど(扁桃炎・咽頭炎・喉頭炎・声帯ポリープ)
小児のいびき・無呼吸や成人の扁桃炎で熱をよく出す患者さんに口蓋扁桃摘出術を行います。
頸部(耳下腺疾患・顎下腺疾患・甲状腺疾患)
頭頸部外科では頸部の手術も行います。耳下腺・顎下腺・甲状腺手術においては、神経麻痺を合併することがあります。それを防ぐためにNIMという神経刺激装置を使用しています。
腫瘍(良性腫瘍~舌癌・喉頭癌などの悪性腫瘍)
鼻副鼻腔癌、舌癌などの口腔癌、咽頭癌、喉頭癌に対して、抗がん剤治療、手術、放射線治療を計画します。
顔面外傷
交通事故などによる顔面骨の骨折にも対応しています。
睡眠時無呼吸症候群
自宅での睡眠中の無呼吸の回数を確認する簡易検査を行います。その結果によっては、1泊入院で脳波や眼球運動などを確認する精密検査を行います。確定診断がなされれば、適切な治療を開始します。
診療実績
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
| 鼓膜チューブ挿入術 | 30 | 36 | 29 |
| 中耳手術(鼓室/鼓膜形成術など) | 27 | 25 | 21 |
| アデノイド切除 | 18 | 15 | 40 |
| 口蓋扁桃摘出術 | 74 | 64 | 73 |
| 内視鏡下副鼻腔手術 | 56 | 41 | 62 |
| 唾液腺腫瘍摘出(耳下腺・顎下腺) | 11 | 15 | 20 |
| 甲状腺手術(良性/悪性腫瘍・バセドウ) | 24 | 31 | 43 |
| 声帯ポリープ・喉頭腫瘍(直達鏡) | 0 | 0 | 5 |
ドクターインタビュー
スタッフ紹介
-
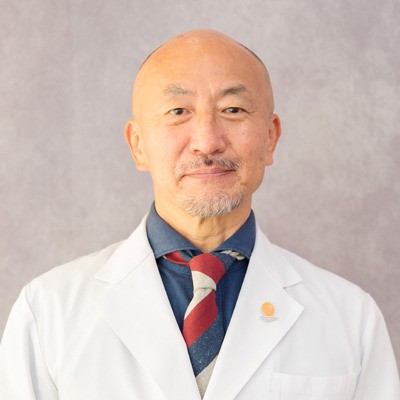
副院長
森部 一穂 もりべ かずほ
資格 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会専門医・指導医 嚥下機能評価研修会修了 補聴器相談医 名古屋市立大学臨床教授 Immediate Care in Rugby Level2 緩和ケア研修会修了 専門分野 耳鼻いんこう科全般 中耳手術 頭頸部腫瘍 -
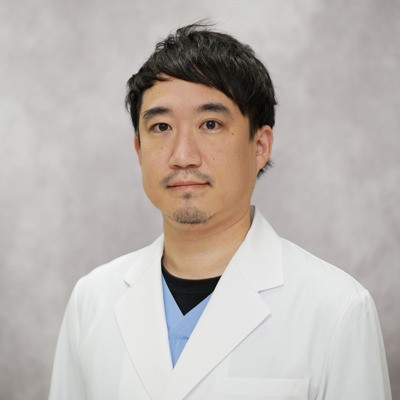
耳鼻いんこう科部長
関谷 真二 せきや しんじ
資格 日本耳鼻咽喉科学会専門医・指導医 緩和ケア研修会終了 嚥下機能評価研修会修了 専門分野 耳鼻いんこう科全般 鼻・副鼻腔手術 頭頸部腫瘍 -
医長
甕 里紗 もたい りさ
資格 日本耳鼻咽喉科学会専門医 嚥下機能評価研修会修了 補聴器相談医 緩和ケア研修会修了 専門分野 耳鼻いんこう科全般 頭頸部腫瘍 -
副医長
高橋 弘恵 たかはし ひろえ
資格 日本耳鼻咽喉科学会専門医 嚥下機能評価研修会修了 補聴器相談医 緩和ケア研修会修了 専門分野 耳鼻いんこう科全般 -
医員
大鹿 颯太 おおしか そうた
専門分野 耳鼻いんこう科全般 -
医員
西脇 海斗 にしわき かいと
専門分野 耳鼻いんこう科全般 -
非常勤医師
蒲谷 嘉代子 かばや かよこ
資格 日本耳鼻咽喉科学会専門医 日本めまい平衡医学会 めまい相談医 専門分野 耳鼻いんこう科全般
外来担当医表
| 診察室 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 午前03 | 森部 | 関谷 | 森部 | 高橋 | 甕 |
| 午前05 (新患) |
関谷 |
大鹿 |
高橋 |
甕 |
西脇 |
| 午前06 | 高橋 | 甕 | 関谷 | 西脇 | 高橋 |
| 午前07 |
西脇 大鹿 |
西脇 |
めまい |
大鹿 | 大鹿 |
| 午後03 (予約) |
特殊 |
||||
| 午後05 | 検査 | 検査 | 検査 | 検査 | |
| 午後06 |
舌下 免疫 |
睡眠時 無呼吸 |
睡眠時 無呼吸 |
||
| 午後07 |
学生 |
学生 |




