概要
当科は2010年の愛知県立循環器呼吸器病センターとの統合以来、一宮市内だけではなく西尾張地区の基幹病院として、広く患者さんを受け入れられるよう努力してきました。また、みなさんの「かかりつけ医」の先生方からの紹介をスムーズに受けるため、循環器医師への直通電話を設置し、すばやく患者さんの診察を行える体制も整えています。
従来の血管内治療(冠動脈インターベンション、カテーテルアブレーションなど)に加え、最新の治療方法も導入しています。2018年よりTAVI(経カテーテル大動脈弁置換術)を選択肢に加え、治療成績も良好です。近年増加傾向にある慢性心不全治療にも力を注いでおり、医師・看護師・薬剤師・リハビリなど多くのスタッフによるサポートを行っています。
「心臓病」と診断されると不安になりがちですが、すべての医師が丁寧な説明を心がけています。
診療内容
虚血性心疾患(急性冠症候群・狭心症)
狭窄した冠動脈を拡張するための手術で、多くはステントという金属を留置します。より重症例にも対応できるよう、ロータブレーター・ELCA(レーザー)・ダイアモンドバック・ショックウェーブなどの治療技術にも対応しています。
慢性下肢閉塞性動脈硬化症
足に血液を送る動脈の狭窄・閉塞に対して、主にカテーテルによる治療を行っています。血管外科との相談のうえ、必要であれば外科的バイパス術を選択することもあります。
不整脈
頻脈性不整脈(脈が異常に速くなる疾患)には、根治を目指したカテーテルアブレーションを、逆に脈が異常に遅くなり失神をきたす徐脈性不整脈には、ペースメーカ植込み(リードレスペースメーカも含む)を積極的に行っています。
致死性不整脈(心室細動など)に対しては植込み型除細動器(ICD)移植のうえ、遠隔モニタリングを利用したきめ細かい管理を行います。また、重症心不全に対する心臓再同期療法(CRT)も多くの症例に導入しています。
重症心不全
PCPS/ECMO(いわゆるエクモ)などの心肺補助システムを駆使した急性期治療を積極的に行っており、より重症例には名古屋大学と連携しつつ心移植を目指すこともあります。
心臓構造疾患
従来は外科治療一択であった重症の大動脈弁狭窄症に対して、TAVI(経カテーテル大動脈弁置換術)やバルーン拡張術を2018年より行っています。その他の先進的治療実施に向けて鋭意準備中です。
その他
レーザーを使用したペースメーカリード抜去術
肥大型心筋症に対するカテーテル治療(PTSMA; 経皮的中隔心筋焼灼術)
透析シャントに対するカテーテル治療(VAIVT)
重症高血圧
急性・慢性肺血栓塞栓症、深部静脈血栓症
原発性肺高血圧症
心臓弁膜症
感染性心内膜炎 など
診療実績
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
| 検査 | 冠動脈造影(CAG) | 901 | 1032 | 787 |
| 心臓超音波検査 | 8832 | 9416 | 12889 | |
| 心臓シンチグラフィー(SPECT) | 684 | 815 | 750 | |
| 冠動脈CT(CCTA) | 978 | 990 | 1119 | |
| 治療 | 経皮的冠動脈形成術(PCI) | 547 | 539 | 463 |
| カテーテルアブレーション | 230 | 229 | 227 | |
| ペースメーカ(移植・交換) | 79 | 99 | 89 | |
| 植込み型除細動器(移植・交換) | 23 | 16 | 22 | |
| 心臓再同期療法(CRT)(移植・交換) | 19 | 24 | 12 | |
| 経カテーテル大動脈弁置換術(TAVI/TAVR) | 47 | 70 | 60 | |
| 経皮的弁形成術(BAV) | 22 | 27 | 8 | |
| ペースメーカーリード抜去 | 6 | 7 | 5 | |
| PTSMA (経皮的中隔心筋焼灼術) | 5 | 3 | 3 | |
| 補助循環 | 経皮的心肺補助(PCPS/ECMO) | 15 | 19 | 31 |
| Impella | 19 | 24 | 16 |
診療科・部門のご案内
診療コラム
スタッフ紹介
-
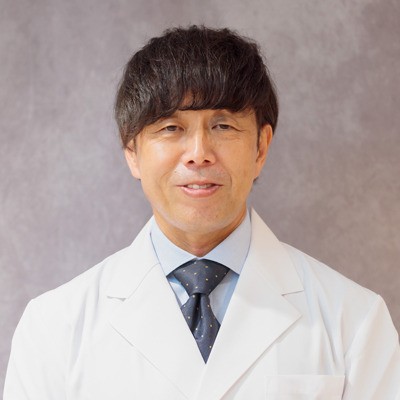
院長
志水 清和 しみず きよかず
資格 日本循環器学会専門医 日本救急医学会専門医 集中治療医学会集中治療専門医 日本内科学会総合内科専門医 日本心血管インターベンション治療学会指導医 植え込み型除細動器・両心室ペースメーカー認定医 日本救急医学会ICLS認定コースディレクター・インストラクター JMECCインストラクター 名古屋大学医学部臨床教授 専門分野 循環器内科全般、心血管内治療 -
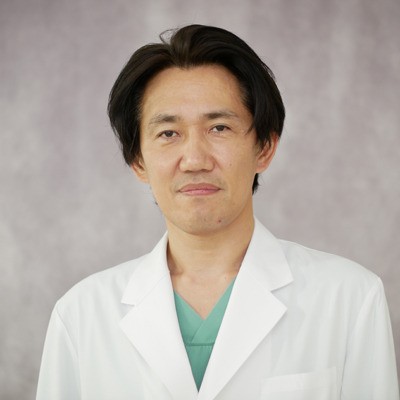
診療局長
石黒 久晶 いしぐろ ひさあき
資格 日本内科学会認定内科医 日本循環器学会専門医 CVIT(日本心血管インターベンション治療学会)専門医 藤田医科大学客員准教授 専門分野 循環器内科全般 心血管内治療 下肢血管内治療 透析シャント治療(VAIVT) ペースメーカーリード抜去術 腎動脈狭窄治療 鎖骨下動脈狭窄治療 肥大型心筋症のカテーテル治療(PTSMA) -
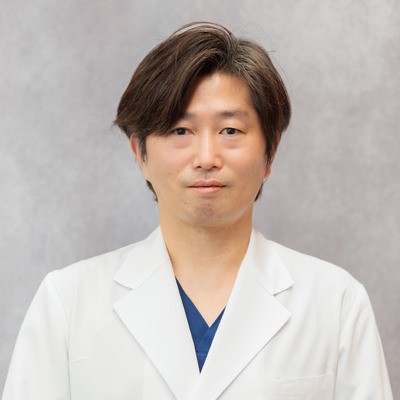
救命救急センター長兼循環器センターICU部長
谷口 俊雄 たにぐち としお
資格 日本循環器学会専門医 日本内科学会認定医 日本内科学会総合内科専門医 日本救急医学会専門医 集中治療医学会集中治療専門医 CVIT認定医 JMECCインストラクター ICLSディレクター MCLSプロバイダーコース修了 hospital MIMMUSプロバイダーコース修了 愛知DMAT,日本DMAT隊員 名古屋大学医学部臨床講師 専門分野 循環器内科全般 救急科全般 -
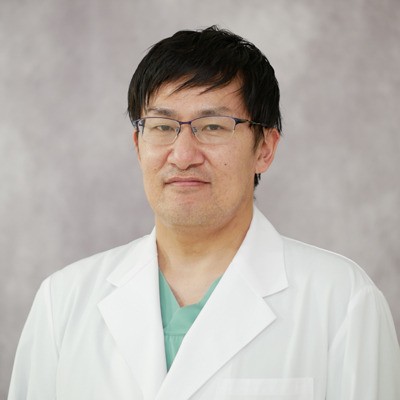
循環器内科部長兼循環器センター長
澤村 昭典 さわむら あきのり
資格 日本循環器学会認定循環器専門医 日本内科学会総合内科専門医 日本医師会認定産業医 緩和ケア研修会修了 ICD/CRTD 埋込認定医 専門分野 重症心不全 補助循環 心不全緩和ケア -
不整脈部長
梅本 紀夫 うめもと のりお
資格 日本内科学会認定医 日本循環器学会専門医 ICD/CRT-D 認定医 専門分野 循環器内科全般 -
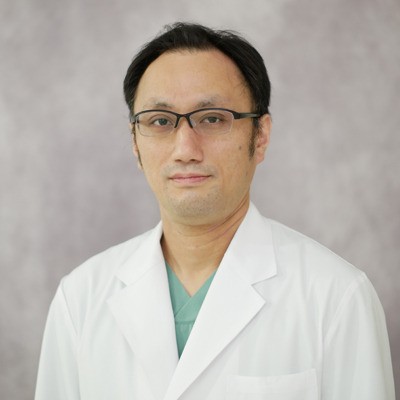
循環器センター心血管内治療部長
田代 詳 たしろ ひろし
資格 日本内科学会総合内科専門医 日本循環器学会専門医 日本心血管インターベンション治療学会認定医 TAVI指導医(Sapien) 日本周術期経食道エコー(JB-POT)認定医 SHD心エコー図認証医 専門分野 循環器内科全般 虚血性心疾患 構造的心疾患 心エコー -
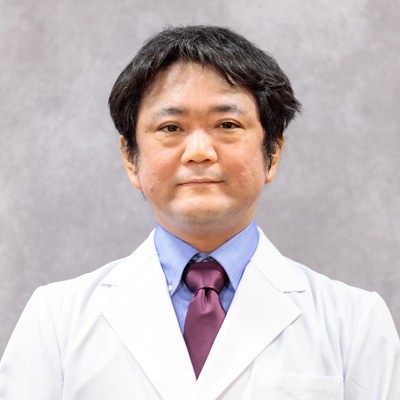
医長
杉浦 剛志 すぎうら つよし
資格 日本内科学会認定医 TAVI指導医(Sapien) 専門分野 循環器内科全般 構造的心疾患 -
医長
山内 良太 やまうち りょうた
資格 日本内科学会認定内科医 日本循環器学会循環器専門医 日本心血管インターベンション治療学会認定医 日本不整脈心電学会認定不整脈専門医 日本周術期経食道心エコー認定試験合格 緩和ケア研修会修了 専門分野 循環器内科全般 心エコー -
医長
徳田 晃太郎 とくだ こうたろう
資格 日本内科学会総合内科専門医 日本内科学会認定内科医 日本循環器学会循環器専門医 日本心血管インターベンション治療学会認定医 日本医師会認定産業医 緩和ケア研修会修了 専門分野 循環器内科全般 -
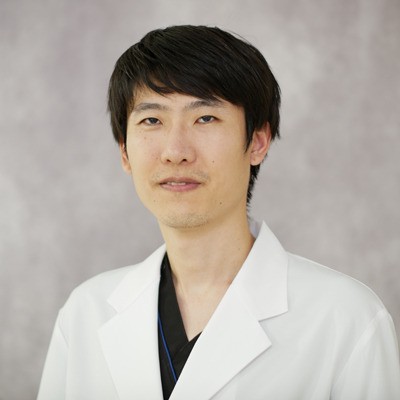
副医長
梶浦 宏紀 かじうら ひろき
資格 日本内科学会専門医 緩和ケア研修会修了 日本循環器学会専門医 CVIT認定医 ICLSインストラクター JMECCインストラクター 専門分野 循環器内科全般 -
医員
今枝 竜三 いまえだ りゅうぞう
資格 緩和ケア研修会修了 専門分野 循環器内科全般 -

医員
棚橋 龍 たなはし りゅう
資格 日本周術期経食道心エコー認定試験合格 JMECC修了 緩和ケア研修会修了 専門分野 循環器内科全般 -
医員
西尾 佳将 にしお けいすけ
資格 緩和ケア研修会修了 専門分野 循環器内科全般 -
医員
石田 唯登 いしだ ゆいと
資格 緩和ケア研修会修了 専門分野 循環器内科全般 -
非常勤医師
安田 信之 やすだ のぶゆき
専門分野 循環器内科全般 -
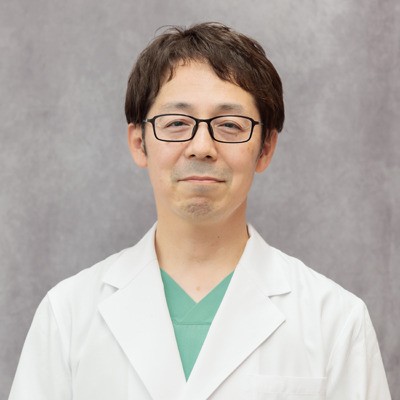
非常勤医師
浅井 徹 あさい とおる
資格 日本内科学会総合内科専門医 日本循環器学会専門医 植え込み型除細動器・両心室ペースメーカー認定医 不整脈専門医 専門分野 循環器内科全般 不整脈治療 植え込み型心臓デバイス
外来担当医表
| 診察室 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 午前01 (新患) |
志水 | 志水 | 志水 | 石黒 | 志水 |
| 午前02 | 梅本 | 山内 | 梶浦 | 安田 | 石黒 |
| 午前03 | 杉浦 | 杉浦 | 杉浦 | 杉浦 | 澤村 |
| 午前05 | 今枝 |
ペース メーカー (第1・2・3週) |
棚橋 | 田代 | 杉浦 |
| 午後 | 不整脈(梅本) | 不整脈(山内) | TAVI | 不整脈 | ICD/CRT |
| SAS |




